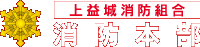令和7年度秋季全国火災予防運動の実施について
令和7年11月9日(日)から11月15日(土)までの7日間で全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。火災予防のための取り組みを地域住民の皆様へお知らせします。火災を発生さないように防火の意識を高めましょう。
防火標語(2025年度全国統一防火標語)
「 急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし 」
1 地震火災の対策について
地震火災を防ぐためには、家具等の転倒防止対策や感震ブレーカーの設置などの事前の対策のほか、地震直後の行動、電気やガスが復旧したあとの対策が地震火災を防ぐために重要となります。次のリーフレット等を参考に日頃からの対策に努めましょう。
※リンク先の動画もご視聴ください。
ゆるサイと 火災・防災 再かくにん | 住宅防火関係(映像資料) | 総務省消防庁
今、備えよう。大規模地震時における電気火災対策 | 住宅防火関係(映像資料) | 総務省消防庁
2 住宅防火対策について
様々な火災の中でも、特に住宅で発生する火災で多数の死者が出ており、その出火原因はたばこ、ストーブ、コンロ、電気機器など、生活する上で身近にある機器が多くを占めます。
日頃から取り組んでいただく住宅防火対策として、4つの習慣、6つの対策からなる「住宅防火いのちを守る10のポイント」が取りまとめられています。
是非、ご家族の皆様で住宅火災からいのちを守るための対策をご確認ください。
※リンク先の動画もご視聴ください。
住宅防火 いのちを守る 10のポイント | 住宅防火関係(映像資料) | 総務省消防庁
3 林野火災対策について
本年2月に岩手県大船渡市において延焼範囲約3370haに及ぶ大規模な林野火災が発生しました。林野火災は人為的要因で発生することが多く、一度発生すると消火が困難になる場合があります。以下のことに注意し林野火災を防ぎましょう。
【林野火災防止のための注意点】
・乾燥・強風の日にたき火や火入れをしない
・火気を使用する際は目を離さない
・火入れ・たき火など火の使用は一人でしない(複数人で実施)
・消火用の水を確保
・使用後は完全に消火
・たばこの投げ捨てや火遊びは厳禁