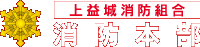管内において火災が多発!火の取扱いに注意しましょう
ここ数日、上益城消防組合の管内において火災が多発しています。今の時期は空気が乾燥し火災が発生しやすく、火災になった場合に延焼拡大する可能性が高くなっています。また、気象庁の情報より、広い範囲で降水量が少ない状況となっており、12月末からの4週間の降水量は、この時期として30年に一度程度の顕著な少雨であり、今後1ヶ月程度は、まとまった降水とならない見込みと示されています。以下の点に注意し、火災を発生させないようにしましょう!
<住宅火災予防のための注意点>
住宅防火いのちを守る10のポイント!(4つの習慣・6つの対策)
【4つの習慣】
1 寝たばこは絶対にしない、させない。
2 ストーブの周りに、燃えやすいものを置かない。
3 こんろを使うときは火のそばを離れない。
4 コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
【6つの対策】
1 ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
2 住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
3 部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する
4 消火器を設置し、使い方を確認しておく
5 お年寄りや体が不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく
6 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う
住宅防火命を守る10のポイント
<林野火災予防のための注意点>
・乾燥・強風の日にたき火や火入れをしない
・火気を使用する際は目を離さない
・火入れ・たき火など火の使用は一人でしない(複数人で実施)
・消火用の水を確保
・使用後は完全に消火
・たばこの投げ捨てや火遊びは厳禁
※お住まいの地域での林野火災注意報・警報発令の情報に注意!
警報発令時は屋外での火の取扱いは行わないでください。
STOP山火事
野焼き火災予防リーフレット